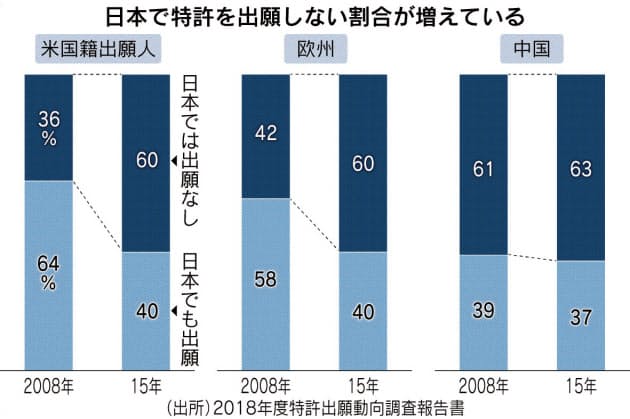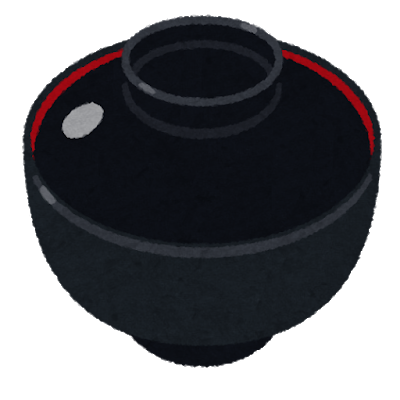本庶教授が「特許使用料が少なすぎる」とオプジーボ特許契約に関して不満を表しているとして各種メディアを騒がせています。
たとえば、日経新聞では、本庶佑・京都大学特別教授と大村智・北里大学特別栄誉教授が、ノーベル賞の受賞対象となった研究成果をもとに製品を出した製薬企業から、それぞれ受け取った特許のおよその対価は「26億円」対「200億円」としています。
この報道については、少しだけ誤解しそうなところがあります。
それは「特許使用料」についてです。
特許使用料というと、通常は特許ライセンス契約を想定すると思いますが、本庶佑教授と小野薬品の関係は「共同出願人」です。
すなわち、ライセンサーとライセンシーの関係にあるわけではありません。
そのため、「特許使用料」という用語には違和感を覚えてしまいます。
正確を期すならば「不実施補償契約」という言葉を使ったほうが適切だったのではと思います。
すなわち、「本来特許権の実施は自由な特許権者のうち、一方が不実施の場合、不実施側が利益を保障してもらうために結ぶ契約」です。
これが本庶佑教授の場合は1%未満だったのかなと思います。
少ないように思えますが、まだ海の物とも山の物ともつかない状況での契約ですから製薬会社にだけ有利というわけでもないでしょう。
さて、もし本庶佑教授の主張が認められた場合、どうなるでしょうか。
たとえば、売上の5%の利益を支払うということを後から認めた場合です。
これは研究者側にとっては嬉しいでしょう。
しかし、製薬会社にとっては恐ろしい結果となります。
将来のことを考えてお互い契約をしているのにその契約が後から覆されてしまうというのでは何のための契約だったのか・・・と恐れ、それなら、と最初は低廉のライセンス料だけにすることが当たり前になってしまうかもしれません。
本来は契約締結前に十分に話し合うべきだったところ、交渉義務を放棄した研究者を過度に保護することになるのではないでしょうか。
もちろん、ここまで有名になり利益を生み出してくれた研究者の労力へ報いたいという気持ちから、製薬会社が特別料を支払うというのはぜひ行ってほしいところですが、契約の改めというのは、認め難いと思ってしまいます。
「研究者は研究だけしていればいいではないか。契約の勉強までしなければいけないのか!」
という意見はあると思います。
しかし、ビジネスの側面がある以上、仕方ないのではないかなと思います。
弁護士等に協力を要請することもできたわけですし。
交渉前に必死で勉強して契約を重ねた大村教授は本庶教授の10倍近くの利益を得ているわけですが、ここから研究者たち、また研究者以外にも全ての知的財産権の権利者たちは、契約の重要性について今一度考えてみても良いと思います。
なお、余談ですが、私も契約を適切に行わず損をしたことがあります。
人は変わるのです・・・(T-T)
今では良い勉強だったと良い方に解釈していますが、もったいないことをしました。
自分が痛い目を見たので、イラストレーターさんなんかには、「契約を結んでおいて!」とよく言っています。
特に、大きい金額になりそうなものは弁護士に依頼してでも作っておくべきですよ!