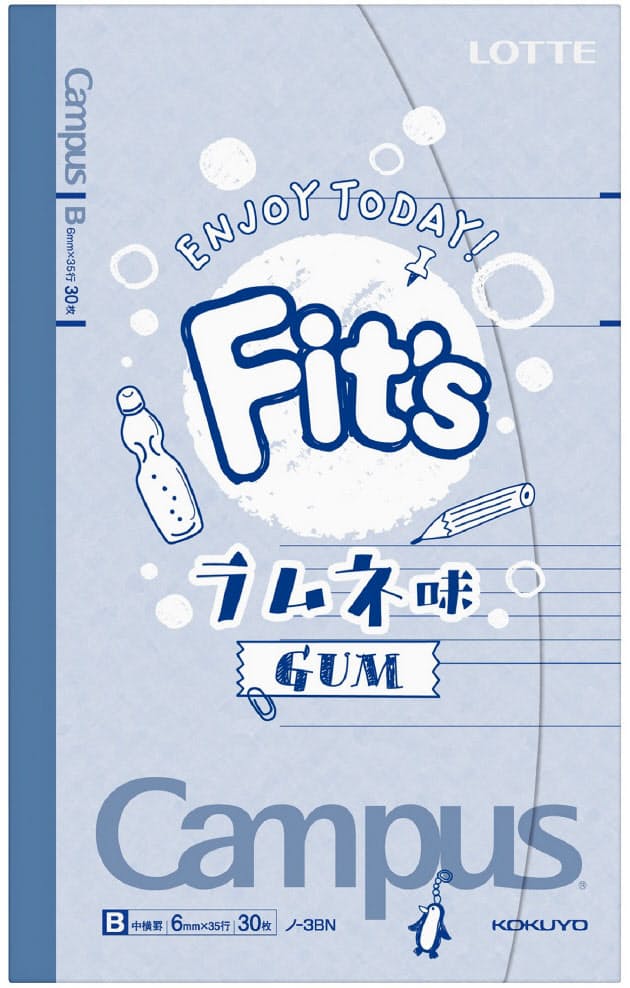Googleが発表した新しいゲームプラットフォーム「Stadia」。
昨日からネットではこの話題で持ち切りです。
ゲームには様々な知的財産権が絡んでくるので、知財ブログとしては触れぬわけにはいかぬじゃろうということでいろいろと調べてみました。
Stadiaと特許
まず、特許についてですが、テックノマドinアジア編集長さんによって米国特許を元にした記事が既に書かれていたので(仕事早っ!)、私は特許以外の知財について触れようと思います。
なお、上記記事について軽く触れておくと、
・ゲームのプレイ状況を共有して他の人がそこからプレイできる「State Share」
・複数プレイヤーによってプレイされた内容が
・自由自在に編集された状態で映像化される
ということが載っています。
ここで言う「自由自在に編集された状態の映像」とは例えば、
・複数人のプレイ画面を切り替えた映像ができるのに加え、
・誰のプレイ画面でもない視野からの映像も挿入できる
・切り取る場面はプレイヤーの状況(敵を倒した、倒されたなど)により自動抽出できる
といった感じです。
プレイ動画をYoutubeにアップすることによりYoutubeの視聴者が増え、視聴者を更にゲームに誘導ということを繰り返すことに寄り、グーグルワールドに人々を閉じ込める(言い方悪いけど)を可能にするので、改めて、世界はグーグルに支配されている!と思いました(笑)
いろいろな検索エンジンが出てきていますが、まだまだグーグルのシェアはダントツですよね。
10年後、20年後の世界はどうなっているのか気になるところです。
Stagiaと商標権
さて、特許について軽く触れた後は、商標についてお話したいと思います。
まず、最初にstadiaという名前を聞いた時に思ったのが、「同じ名前のサービス、たくさんあるんじゃないの?」ということです。
英語をベースにした言葉って既に商標登録されてしまっている場合が多いので・・・。
そこで、日本での商標登録について調べてみると、あるわあるわ、たくさんの商標登録が存在していました。
以下は一例です(指定商品は電子計算機用プログラムなど)。
・電通の「STADIA」
・ECCの「スタディア」
・ワイイーシーソリューションズの「Stagia」
・日産の「STAGEA」
googleが日本でStadiaのサービス提供を開始すると、各社には商標使用料が入ってくることになりそうです。
iPhoneのおかげでアイホンに商標使用料が入っているみたいにお得ですね〜(笑)
私が商標ゴロだったら、確実にStadiaで商標登録出願してたわ!!(笑)
ベストライセンスさんがStadiaで商標登録出願するに500ギル賭けておきます。
知財以外の話
Stadiaの大きな魅力は、「ハードを問わない」「いつでもどこでもプレイできる」ということです。
これは、たとえば「ペルソナ5をやってペルソナファンになった人がペルソナ4をやってみようと思ってもプレステ本体の互換性が無いためにソフトを買ってもプレイできない」という悲劇を防げます。
また、レトロゲームをやりたくてもハードを選ぶために、仕方なく一つのソフトのためだけに64を買うということもしなくて済むのでとても便利です。
(上記2つについては過去記事を御覧ください。個人的な悲しみを綴っております。)
が、この魅力は見方を変えれば逆にデメリットでもあります。
たとえば、「オンラインに繋がっていればプレイできる」⇒オフラインではプレイできない & オンラインで知らない人と知り合いたくないのに知り合ってしまう
というデメリットを含んでいます。
ドラクエやモンハンのようにオンラインゲームをして知らない人と出会うのが楽しいという人にはそれはそれで良いんですよ。
(ゴマキ(モー娘)に会えるかもしれませんし!w)
でも、純粋にゲームを楽しみたいだけの人もいますよね。
ドラクエ10(オンラインゲーム)よりも、ドラクエ11(オンラインゲームではない)の方が好きという人もたくさんいることでしょう。
そんな人にとってはオンライン環境って悩ましい存在です。
女性キャラにすると男性が寄ってくるということでネカマプレイしている人もたくさんいるということですし、臨機応変にプレイを楽しむのも良いと思いますが・・・。
というわけでいろいろとどうでもいいことを書いてしまいましたが、Stadiaの日本上陸、楽しみです!